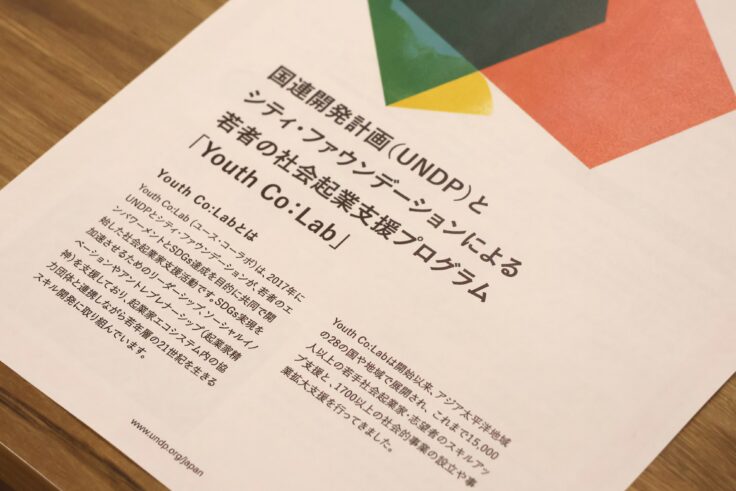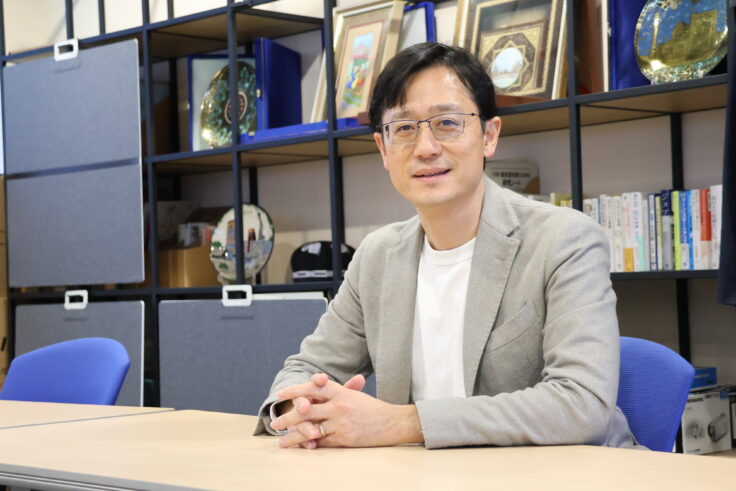デザインで コーヒーの新たな価値を創造

うまみや香りを損なわずカフェインだけを選択的に除去したデカフェ(カフェインレス)コーヒーで、生産国と消費国の課題解決を目指すストーリーライン株式会社。「サスティナブルな未来のデザイン」を目指すCEOの岩井順子さんにお話を伺いました。
どんなイノベーションを目指しているか
独自のプロセスでおいしいデカフェを
コロナ禍以降、日本国内では健康意識が高まっています。食品の機能性に着目した商品がたくさん出ており、心や体のコンディションを毎日の生活の中でコントロールしたいという消費者ニーズを感じます。私たちはその中でカフェインの機能性に着目しています。
デカフェ(カフェインレス)コーヒーを飲んだことはありますか。日本は世界第4位のコーヒー消費国ですが、コーヒー全体に対するデカフェの輸入量は0・6~7%程度しかありません。日本でデカフェ商品は一般に「値段が高くてまずい」というイメージがあるかもしれません。飲んだことがある人も少ないですし、飲んだ人からはネガティブなイメージを持たれているのがデカフェコーヒーの現状です。
美味しくない理由は二つあり、一つは技術の問題です。カフェインを除去する際に糖質や脂質、酸味などが一緒に抜けてしまっているのです。私たちは、特殊な有効成分を選択的に抽出する「超臨界CO2抽出」という抽出技術をカフェインに応用しています。超臨界CO2とは、一定の温度と圧力を加えることによって気体と液体の両方の性質を併せ持った状態のCO2のことで、この状態のCO2を抽出に利用することで香気成分やうまみが抜けない、カフェインだけを選択的に除去したコーヒーを作っています。
もう一つは流通の問題です。デカフェの加工は主にカナダ、ドイツの2社で行われています。例えば東アフリカでとれたコーヒーをデカフェにする場合、一旦カナダかドイツに運び、そこから消費国に輸入します。先進国基準の加工料や運送コストがかかり、事業者側はそれに対応するため原料の品質を下げるので、おいしいわけがないのです。
解決のために原産国でのデカフェ生産を目指しています。私たちが着目しているのはルワンダ。手間暇かけていいものを作っても儲かるのは中間事業者という、植民地時代の利益構造がなかなか崩せません。しかし、ここに技術を投入すれば変えられます。デカフェというオプションをつけることでアフリカの農業を第一次産業から第二次産業化していくことも目指します。

これまでの歩み
私はデザイン一筋で、学生時代はデザイナーになることだけを考えてまっしぐら。美大のデザイン科に進学してデザイナーになりました。最初はもののデザインをする仕事をしていましたが、作り続けているうちになぜこれを作るのかという疑問が出てきました。ずっと図面やスケッチを描いているよりもこれがなぜ必要なのかというストーリーに興味が生まれ、企画の道に進みました。企業勤めはそれほど長くはなく、そのあとはフリーランスとして企業の商品企画を手掛けてきました。その後アメリカのデザインファームから声がかかり渡米します。体系化されたユーザーリサーチのやり方や分析の仕方、どうコンセプトにつなげるかといった手法はそこで学びました。フィーリングではなくて理論的に進めるやり方を学び、帰国後はそれを日本の企業向けに行いました。
もともとコーヒーは好きでした。アメリカで住んでいたポートランドはコーヒーが盛んで、私も自分の好みで楽しんでいました。帰国後、娘の妊娠中に初めてデカフェコーヒーを飲みましたが、あまりの不味さに驚きました。ちょうど次のビジネスネタを探していた時期と合致して、おいしくない背景を調べてみると、技術や流通の課題が見えてきました。同時に超臨界抽出という技術を知り、これをうまく使えば、ユーザーのニーズを満たすおいしいコーヒーができるのではないかと考えました。知り合いを介して東北大の研究室とつながり、共同研究を進めています。
会社は2018年に創業し6期目。東京都に本社があり、仙台市の東北大学の敷地内に自社ラボがあります。昨年10月には都内に「CHOOZE COFFEE(チューズコーヒー)」というブランド名でカフェイン量が選べるというコンセプトで実証店舗を出しました。

アイデア・技術を実現するために
テクノロジーは私の専門ではありませんが、テクノロジーをどのように届けるかは私が専門とするサービスデザインの分野です。テクノロジーとデザインを掛け合わせることで新たな価値が生まれます。
以前はデカフェか普通のコーヒーかという選択の仕方だったので、健康上の理由や妊娠、授乳中などの理由がなければデカフェを誰も選びませんでした。
これからは、ユーザーに提供する価値をデザインし直す必要があります。デカフェという形では価値を提供するのではなく、普通のおいしいコーヒーの選択肢が増えるという価値の転換をやっていくのがデザインだと思います。
「チューズコーヒー」の今年6月までの売り上げデータを見てみると、レギュラーが約6割、低カフェインとデカフェを足すと38・4%という結果でした。この店では確かな数値を取るためにあえてデカフェをおすすめしていませんが、顧客の約4割が何らかの形でカフェインを減らそうとしている。デカフェの顕在的な市場はまだ小さいですが、カフェインコントロールには4割近い市場があるのではとみています。
そして、それをわかりやすく伝えるための工夫もしています。「チューズコーヒー」の店舗は、あえてビジネスパーソンの多い日本橋にあり、すべてのメニューのドリンクでカフェイン量を選べます。提供するカップは赤がレギュラー、青がハーフ(低カフェイン)、緑がデカフェと色分けてしています。これは視覚的な認知度を上げるためです。
日本橋に勤める人は洗練されたものに対して需要があるだろうと、お店のデザインもガラス張りで店内が見えるようにしており、あえてコーヒー屋さんらしくしていない。カップに使った3色が目立つよう、なるべく色を使わない工夫をしています。無機質な中にも安らぎを提供できるよう、スタッフへの教育も気を配っています。

未来へ向けて・高校生へのメッセージ
コーヒーに携わるものとしてサステナブルな未来を考えています。世界が資本主義の手法で成長してきた中で、搾取経済や不公平などのひずみが生まれました。それはなかなか崩せませんが、インターネット等が普及することで時代が変わってきました。みんなが現状を知り、改善に取り組むべき時代が来ています。
大企業ではありませんので繋がっているのはほんの数社ですが、現状をアップデートするには何かを仕掛けることが必要です。デカフェという技術を使っていいモデルができたという小さい成功例を示していきたい。これが合理的でみんなが幸せになるなら必ず真似する人が出てくるはずです。
また、サステナブルな未来を作っていくためには、消費者の考え方をシフトさせる必要もあります。企業がなんとかするだけではなく個人の問題としてとらえることです。今までは安くていいものを選んでいたけれど、あえてサステナブルで高い商品を選ぶ、それは個人がサステナブルな仕組みに投資していることになります。「コーヒーは安くておいしければいいから、生産者はどうでもいい」という考えでは何も変わりません。高校生のみなさんも自分がものを買ったり、利用しているサービスにお金を払ったりするときには「いい選択ができているか」を考えてみてほしい。それが世の中を変えていきます。
消費者としてだけでなく、自分がムーブメントをつくる起業という選択もあります。ビジネスなので儲かることはもちろんですが、それによって周りを幸せにすることもできると思います。

編集後記
日本で生まれた技術を活用し、サステナブルな未来を描く岩井さん。高校生へのおすすめの本は「サステナブル資本主義」(祥伝社)だそうです。消費者の一員として未来をよくする選択をしていきたいですね。